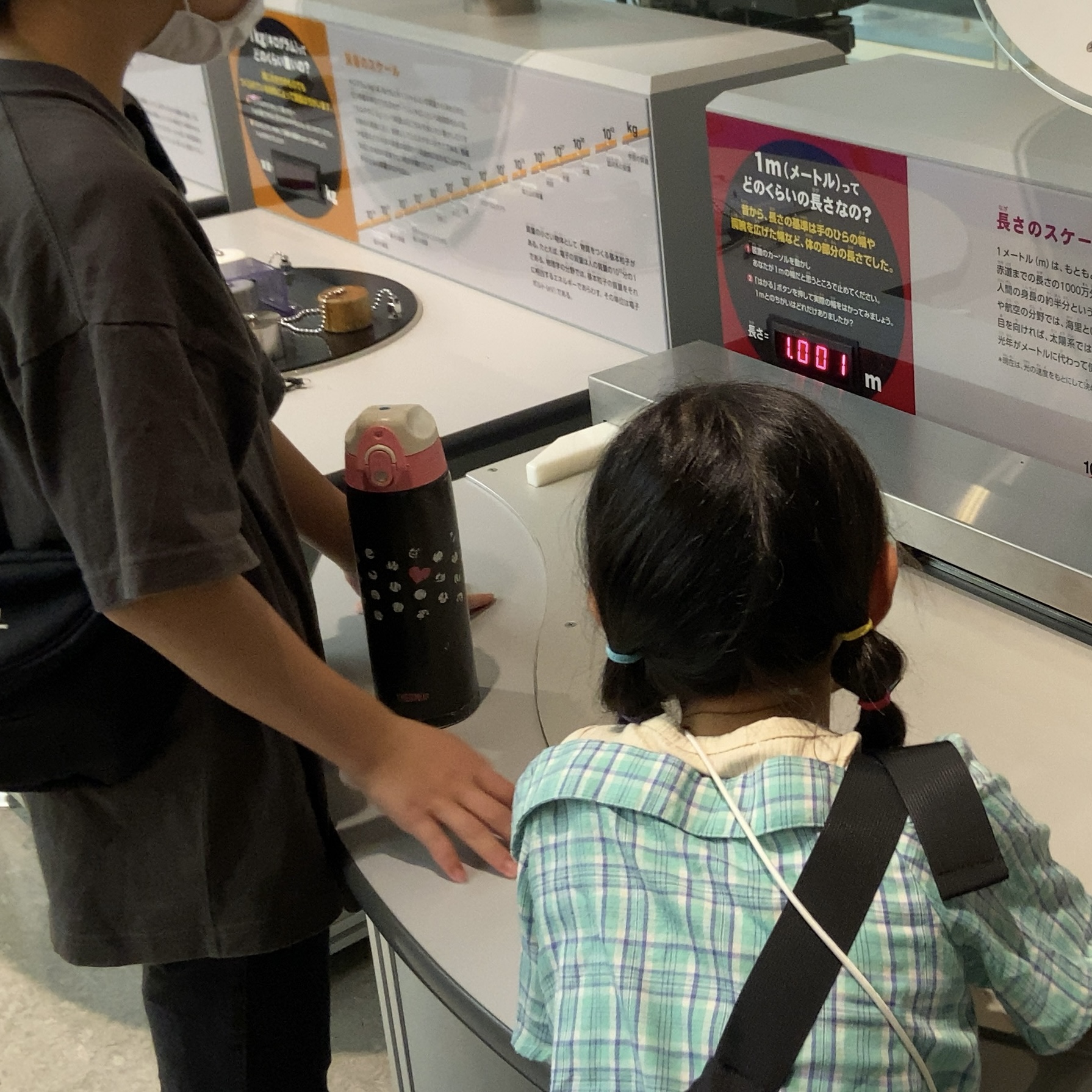今月は、多くの保護者さまが悩む「トイトレ」についてお話させていただきます。
排泄の自立のための学び
「トイレットラーニング」
一般に「トイレトレーニング(トイトレ)」と呼ばれている「おむつ外し」
すんなりおむつを卒業するお子さまもいる一方で、
苦戦を強いられストレスを抱えるご家庭も多いですね。
排泄の自立のための学びを、
モンテッソーリ教育では「トイレットラーニング」と呼んでいます。
訓練して教わる「トレーニング」ではなく、
自ら排泄をコントロールすることを学ぶものだからです。
そもそも生きものは、
開放空間で排泄する能力を持って生まれてきます。
人間は大人の都合によって、
おむつの中で排泄することを学習させられていると言えるかもしれません。
排泄という生理現象を、
五感で認識していれば、
溜める感覚が育まれていきます。
でも、
おむつ内での排泄によって
開放空間での排泄の感覚を失ってしまうと、
排泄を認識し辛くなってしまいます。
だから、おむつの外(開放空間)で排泄することを再学習する必要があるのです。
本来、排泄の自立に適した敏感期は
1歳半~2歳ごろ
経済発展が遅れている地域では、
0歳からおむつをほとんど使わずに
動物として自然な排泄をして育っています。
そういった国では、
1歳半~2歳ごろには排泄が自然に自立しているといいます。
一方で、
日本や欧米ではおむつ外し年齢が年々上昇しています。
欧米のとある小学校では、
1年生クラスの3分の1が
パンツタイプの紙おむつをはいていたというお話も聞きます。
排泄の自立のための4条件
排泄の自立には、
4つの条件がそろう必要があります。
- 運動能力の発達により、自立歩行ができる
- 排泄を認識し、「ちっち」「うんち」など教えることができる
- 内臓感覚の発達により、溜めることができる(排尿間隔が2時間以上が目安)
- 社会性の意識の発達により、「トイレで排泄する」というルールが分かる
紙おむつの性能がよくなり、
排泄を認識し辛くなると、
溜める感覚も発達しにくくなるため、
排泄の自立が遅れる原因になっています。
さらに、
おむつという閉鎖空間での排泄に慣れてしまうと、
開放空間で排泄することに難しさを感じてしまうことも多いようです。
「トイレットラーニング」大人の心構え
おむつの外で排泄することは、
排泄という生理現象の対処を学び直している
ということを心に留めてあげてください。
特に月齢が上がり社会性の意識が発達してくると、
本当はトイレでしたいのにうまくできないからと、
トイレに行きたがらないことも出てきます。
大人サイズのトイレがやりにくいのであれば、
おまるでもよいですね。
座って排泄する練習です。
また、
「おもらし」は学びのプロセスである
という意識も大切です。
濡れて気持ちが悪い感覚(触覚)、
濡れた見た目の変化(視覚)、
臭い(嗅覚)など
五感で感じながら、排泄を認識していきます。
おむつを外すなら夏がおすすめ
と言われることも多いのですが、
お子さまに適した環境はそれぞれです。
あまり決めつけず、
保護者さまとお子さま自身が取り入れやすいタイミングにチャレンジすることをお勧めします。
1977年生まれ、東京都八王子市出身。プロフィール

ママヴィまなびのキ 代表|桑原 眞理子
工学院大学 工学部 応用科学科卒。
企業での商品開発・マーケティングに17年間従事し、暮らしに寄り添う価値づくりを追求する中で、子どもたちの自由な発想と出会い、「子どもの力を社会に届けたい」と強く感じ、教育の道へ。
モンテッソーリ教育を学び、2019年より東京都府中市にてモンテッソーリ教室「マヴィのおうち」を主宰。保育士資格と実践経験を活かし、家庭教育支援と探究的な学びの場づくりを行ってきた。
現在は、「五感をひらく暮らし」と「問いを育む学び」をかけ合わせた「古民家留学こどもMBA」を展開し、地域の自然や文化と出会うリアルな探究体験を届けている。
自らもがん闘病の中で“今を生きる問い”と向き合いながら、教材開発や社会起業へと挑戦中。教育を社会インフラとして広げることをビジョンに掲げ、子どもたちに“わたしを生きる力”を届けるための実践を重ねている。
【資格・活動】
日本モンテッソーリ教育総合研究所認定 3-6歳教師
保育士
日本野菜ソムリエ協会認定 野菜ソムリエプロ
Mariko Kuwabara
Montessori-based / Japan
Learning starts with “ん?” not “Aha!”