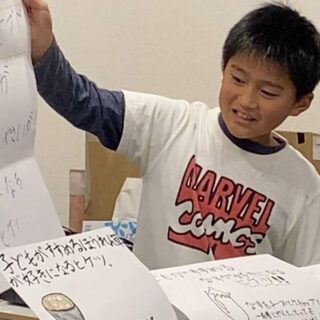幼児期のお子さまについての質問で、年齢問わず共通していることに「間違いの正し方」があるように感じております。
もし、お子さまに「正しくできるようになってほしい」と思うことがあったら、まずは、正しくできないプロセスを大切にしていただきたいと思っています。
それは、子どもには自己訂正する力があるからです。
今回は、自己訂正の大切さと、それが発揮できる関わり方や環境づくりについてお話させていただきます。
子どもの間違いを
正したくなるのはなぜ?
いきなりお箸でご飯を食べることも、
正しく鉛筆を持って、文字を書くこともできません。
そんなことは分かっていても、
お子さまが間違えていると
「違うでしょ…」と言いたくなってしまうものですよね。
なぜでしょうか?
きっと…
変な癖がつくと後で大変だから とか、
大人が訂正する方が
ショートカットでできるようになると思うから
など、お子さまのためを思ってこそだと思うのです。
結果よりもプロセスを楽しむお子さまにとって
試行錯誤は大切な経験です。
遠回りするからこそ、自分で気づくことができるもの。
子どもには、自分で誤りに気づく力がある
それを知っていれば、
向き合い方も変わってくるのではないでしょうか。
大人が訂正するのは簡単だけど…
そもそも、いきなりできるようになることはありません。
なかなか思うようにいかなくて癇癪を起こされることもあると、
大人が代行して訂正をするのが、
その場では一番楽な解決法かもしれませんね。
では、ここで大人が訂正するリスクを考えてみましょう。
大人が先回りしてしまうと、
子どもが自分で誤りに気づくチャンスを失ってしまいます。
やることなすこと「違う」と言われると、
自分にはできないと諦めてやる気を失ってしまいます。
自分でやらなくても、
誰かが先回りしてやってくれるという経験が続くと、
できるようになっているはずの頃には、
他人に依存するようになってしまうのです。
根気強く正しい姿を見せ続けるのが
大人の役目
お子さまが自分で誤りに気づくまでには、
時間がかかります。
今何ができて、
どこに難しさをかんじているのでしょうか?
うまくいかないのは、なぜでしょうか?
まだ身体の準備ができていないのかもしれません。
何が正しいことなのかが、まだ分からないのかもしれません。
構ってほしくて、わざと間違えているのかもしれません。
お子さまを観察して、今の課題を考察します。
そして、根気強く正しい姿を見せ続けてください。
元々、模倣が得意な幼児期は、
何度も目にしたことを再現しようと試行錯誤しています。
自分が主役となって、じっくり取り組んでいると、
少しずつ「何かが違う」
ということにも気づくようになります。
訂正方法が分からないときも、
先回りせずに、助けを求められるまで見守る余裕が大切です。
社会のルールは、
毅然とした態度で伝える
ときに危険なことや、
他人に迷惑をかけるような誤りをしてしまうこともあると思います。
例えば、
机の上に登ったり、
公共の場でわざと大声を出したり…
本人の意志でやったことだけでなく
前を見ずに走っていて人にぶつかるようなこともあるかもしれませんね。
わざとやったことでなかったとしても、
よいことと悪いことの基準を伝えるのは大人の役割です。
ただ「ダメでしょ!」と静止するのではなく、
なぜダメなのかの理由を冷静に伝えることが大切です。
それでもやめない場合は、
理由の意味が分からなかったのかもしれません。
構ってほしくて、わざとやっているのかもしれません。
やめない理由が何かを考え、
お子さま自身で誤りに気づくにはどうしたらよいか
そんな視点で向き合ってみてください。
プロフィール

ママヴィまなびのキ 代表|桑原 眞理子
1977年生まれ、東京都八王子市出身。
工学院大学 工学部 応用科学科卒。
企業での商品開発・マーケティングに17年間従事し、暮らしに寄り添う価値づくりを追求する中で、子どもたちの自由な発想と出会い、「子どもの力を社会に届けたい」と強く感じ、教育の道へ。
モンテッソーリ教育を学び、2019年より東京都府中市にてモンテッソーリ教室「マヴィのおうち」を主宰。保育士資格と実践経験を活かし、家庭教育支援と探究的な学びの場づくりを行ってきた。
現在は、「五感をひらく暮らし」と「問いを育む学び」をかけ合わせた「古民家留学こどもMBA」を展開し、地域の自然や文化と出会うリアルな探究体験を届けている。
自らもがん闘病の中で“今を生きる問い”と向き合いながら、教材開発や社会起業へと挑戦中。教育を社会インフラとして広げることをビジョンに掲げ、子どもたちに“わたしを生きる力”を届けるための実践を重ねている。
【資格・活動】
日本モンテッソーリ教育総合研究所認定 3-6歳教師
保育士
日本野菜ソムリエ協会認定 野菜ソムリエプロ
Mariko Kuwabara
Montessori-based / Japan
Learning starts with “ん?” not “Aha!”